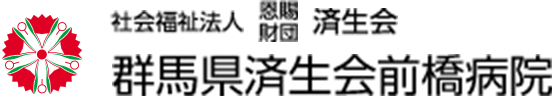診療部門のご案内Departments and Divisions 循環器内科
はじめに
循環器内科では、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞など)、不整脈、心不全(弁膜症・心筋梗塞・先天性心疾患など)、血圧の疾患(高血圧・低血圧など)、動脈・静脈疾患(大動脈瘤・閉塞性動脈硬化症・静脈血栓症・肺動脈血栓塞栓症など)、肺循環障害(肺高血圧症)、さらには循環器疾患に大きな影響を与える睡眠障害(睡眠時無呼吸低呼吸症候群)等の疾患を対象として診療を行なっております。
循環器疾患は、急性心筋梗塞・急性心不全に代表されるような緊急疾患が多いのが特徴です。当科では24時間緊急対応できる体制をとり、常時最速・最良の循環器診療をめざしております。
特徴
循環器疾患全般の診療を行っておりますが、中でも心臓疾患の大きな要因となる動脈硬化性疾患の治療に力点を置いています。じつは、動脈硬化の治療には「目に見える治療」と「目に見えない治療」があります。
「目に見える治療」
動脈硬化がある程度進むと「臨床症状」が出現します。心臓だったら冠動脈硬化症による狭心症(動いた時に胸が苦しくなる)、末梢動脈だったら下肢筋肉の血流不足による間欠性跛行(歩いた時に足が重だるくなる)等です。さらに進行して血流が途絶すると「臓器障害」に至ります。心臓だったら心筋梗塞、脳の場合は脳梗塞、末梢動脈では潰瘍・壊疽がこれに相当します。「目に見える治療」はその動脈硬化巣に対する局所治療です。狭窄あるいは閉塞している血管局所をバルーンやステントを用いて拡張させ、血流を確保するための治療です。脳血管は脳外科の先生が治療されますが、我々循環器内科では冠動脈や末梢血管を治療します。循環器医療の“花形”とされる分野で、患者さんにもわかりやすくまた治療効果がすぐに実感されます。ただし残念ながら、病院間で治療の基準(適応)や技術が異なるため注意が必要です。治療を受ける側の“アンテナ”も重要と思われます。当院では2年前に診療スタッフが入れ替わり、より高度な医療技術が提供できるようになりました。その結果、冠動脈治療(PCI)・末梢動脈治療(PTA)が増加し、冠動脈バイパス手術は減少しています。
「目に見えない治療」
我が国で動脈硬化性疾患が急増している背景として高齢化の他に生活習慣の欧米化が挙げられます。具体的には高血圧症・糖尿病・脂質異常症・メタボリック症候群・喫煙等が動脈硬化の進展に関与することがわかっています。生活習慣の是正、適切な薬物療法を選択・継続し、これらの危険因子をコントロールすることによって動脈硬化の進行予防が可能となります。動脈硬化の予防は病気の発症予防(一次予防)と再発予防(二次予防)に大別されます。当然、患者さんのリスクに応じた治療の“さじ加減が”必要となりますが、「目に見えない治療」は 「目に見える治療」のような派手さはありません。しかし局所を拡げるのではなく全身の血管を「守る」ことができます。局所治療は生命予後を延ばすことはできませんが、予防医療には寿命を延ばす沢山の臨床試験が報告されています。無症状の患者さんにモチベーションを維持して頂くのは容易ではありませんが、十分な情報を共有することで個々の症例に適合したリスク管理を行っています。
また透析患者さんに対する血管内治療も当科の特徴の一つです。当院透析センターと協力し、前橋市・伊勢崎市などの他病院から患者さんを積極的に受け入れています。PCI症例の中で透析症例が占める比率は、全国平均:約5%に対し当科では約20%と非常に高率です。また透析に欠かせない動静脈シャント(内シャント)の機能不全に対する血管内治療も開始、現在までの成功率は99.5%と他施設に類を見ない良好な成績を収めています。 さらに心臓疾患の病態解明に欠かせない心臓超音波検査については、群馬大学附属病院から心臓超音波専門医の派遣を頂き、またソノグラファーの人的交流をはかり、年を追うごとに診断精度が向上しています。
2012年より冠疾患集中治療室(Coronary Care Unit;CCU)を併設しました。CCU(写真)には心臓疾患の急性期症例を収容し、循環器医療に精通した医師・病棟スタッフ・臨床工学技師たちによる24時間の徹底した医療・看護が続けられます。

一方、CCU併設に伴って一般病棟のベッド数が減少し、より効率的な診療体制が求められるようになりました。その結果、入院患者数が増加しているにも関わらず、症例あたりの在院日数は減少しています。
診療内容での変化としては末梢血管に対する血管内治療(PTA)の増加が挙げられます。特に閉塞性動脈硬化症(下肢動脈の狭窄・閉塞)と内シャントに対するPTAが増加しています。
【動脈に対するPTA】




【内シャントに対するPTA】


2019~2023年度の診療実績
入院患者数
| 年度 |
入院患者数(延べ) |
平均在院日数 |
|---|---|---|
| 2019 | 11,780 | 32.2 |
| 2020 | 13,832 | 35.1 |
| 2021 | 12,452 | 31.5 |
| 2022 | 11,317 | 28.4 |
| 2023 | 12,282 | 31.1 |
経皮的冠動脈インターベンション (PCI)
| 年度 | PCI件数 | PCI成功率 |
|---|---|---|
| 2019 | 208 | 98.4 |
| 2020 | 194 | 98.4 |
| 2021 | 210 | 95.8 |
| 2022 | 213 | 96.0 |
| 2023 | 176 | 96.6 |
| 年度 | 末梢動脈 | 内シャント |
|---|---|---|
| 2019 | 57 | 192 |
| 2020 | 39 | 184 |
| 2021 | 36 | 185 |
| 2022 | 36 | 148 |
| 2023 | 44 | 115 |
睡眠時無呼吸症候群(SAS)
2003年2月の山陽新幹線の運転士が居眠りをして運転していたという出来事や、アメリカのスペースシャトル、チャレンジャー号事故などは背景に睡眠時無呼吸症候群(SAS)が関与していたと言われております。また車の居眠り運転による事故にも深く睡眠時無呼吸症候群が関連していると言われております。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は睡眠中に呼吸が一時的に止まったり弱くなったりする病気で、大きないびきをかくという特徴が見られます。いびきをかく人の約7割にSASが合併していると言われており、成人男性の4~5%、成人女性の2%に見られるという報告があります。SASを持っていると、いびきなどで周囲の人に迷惑をかけたり、すっきりしない目覚めや頭痛、集中力の低下、よくうつ気分などの症状きたして、日常生活に困るということがあります。しかしそれ以上に大事な事は、SASを持っていると高血圧、不整脈、心筋梗塞、心不全、糖尿病、脳梗塞、脳出血といった循環器疾患や脳血管疾患になりやすい事です。
SASにも色々なタイプがありますが大部分は閉塞型睡眠時無呼吸症候群(OSAS)といって、口腔内や鼻腔、咽頭喉頭が何らかの原因で狭窄、閉塞して起きる病気です。肥満や首が短く太い人、顎の小さい人、舌や軟口蓋、扁桃腺が肥大している人におきやすいと言われています。下記のような症状がある場合、睡眠障害外来に一度ご相談ください。
SASが疑われる症状
1)昼間いつも眠い
2)いくら寝ても眠い
3)朝の目覚めがすっきりしない
4)朝起きると頭が痛い
5)日中よく居眠りをする
6)記憶力や集中力が落ちてきた
7)夜間何度か目を覚まし、何回もトイレに行く
8)いびきがうるさいと言われる
9)精神的に不安定になる(例えば、うつ状態)
SASの診断
まず外来で患者さんの病状を聞き、診察をします。
次に、SASのスクリーニングテストとして、パルスウオッチ検査(一晩指先を流れる血液中の酸素飽和度を調べる検査)をおこない、疑わしい場合は次のステップに進みます。
通常は1日入院していただき、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)を受けていただきます(検査当日は午後3時半頃に入院、翌朝6時過ぎに検査終了となります)。
入院が無理な場合は簡易型PSG検査を自宅でおこなっていただきます。
SASの治療
閉塞型睡眠時無呼吸症候群(OSAS)の治療でまず大事なのは、多くの場合、合併している肥満の改善です。これが根本的な治療です。
現在OSASに有効と言われている治療としてNasal(鼻)-CPAPという治療機器があり、その導入を第一選択で検討いたします。場合によってはスリープスプリントというマウスピース口腔内装着をすすめることがあります。また中枢型睡眠時無呼吸症候群(CSAS)や心不全の治療としてASVという簡易型人工呼吸器導入も行っています。
| 2023年度検査、治療実績 | |
|---|---|
| PSG検査 | 32例 |
| 簡易型PSG検査 | 33例 |
| Nasal-CPAP治療 | 273例 |
| ASV治療 | 11例 |
| 新規CPAP,ASV導入 | 24例 |
肥満で、頭痛持ち、すぐ居眠りをしてしまう、夜間何度も目が覚めてしまう、いびきがうるさいといった症状がありましたら、循環器内科睡眠障害外来を一度受診してみてください(第1~4の金曜日午前:福田)。